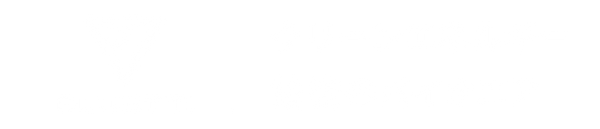春という言葉から、どんなイメージが頭に浮かぶでしょうか。お花見や入学式、それから桜や菜の花など、連想できるものは数多くあります。別れと出会いが交錯し、新しい生活がスタートする季節とも言えますね。本記事では、春ならではの旬の食材や花、それにイベントや行事についてまとめました。
春の食べ物
桜餅

桜の葉で巻かれた和菓子が桜餅です。ひな祭りにも登場する、おなじみの春の季語と言えるでしょう。
桜餅には、大きく分けて2種類があることをご存じでしょうか。実は関東風桜餅のことを長命寺餅(ちょうめいじもち)、一般的によく知られる桜餅のことを道明寺餅(どうみょうじもち)といいます。
一般的には、大きめに砕いたピンク色のもち米でこしあんを包む「道明寺餅」が広く知られています。一方、「長命寺餅」は東京都向島の名物で、クレープ状の生地でこしあんを巻いたスタイルです。とくに香りが強いオオシマザクラの葉を塩漬けにし、桜餅を包むために用いています。
たけのこ
タケノコとは、地下に伸びる茎から出てくる若い芽を指した名称です。土の上に顔を出すかどうかという短いタイミングでやわらかく食べやすいのが特長でしょう。掘りたてなら生で味わうこともでき、ふつうはゆでたり焼いたりして調理されます。独特の香りとシャキッとした歯ごたえが魅力。
春キャベツ
キャベツは日本各地で一年を通じて栽培されていますが、早春から初夏に収穫される品種が「春キャベツ」です。巻きがゆるくて柔らかく、水分を多く含むために生で食べるとおいしさを実感しやすいでしょう。群馬県の嬬恋村などが主な産地として知られています。
カツオ

古代の日本では税としても最高級品に位置づけられ、漁が盛んな地域から朝廷へ納められていたようです。江戸時代の頃には初夏に獲れる「初ガツオ」がたいへん珍重され、口にすることが大変な誇りとされていました。刺身や照り焼きなど多様な料理で食され、かつお節を作る材料としても欠かせません。特に高知県あたりが一大産地として有名です。
新茶
その年に初めて摘み取った若芽を用いて作られるお茶のことです。こってりとしながらも新鮮で爽快な風味が持ち味でしょう。四月から五月にかけての限られたシーズンだけ味わえるため、年間でも最上のおいしさと評価されています。
ハマグリ

アサリより大ぶりで、身が柔らかく旨みが詰まったハマグリ。産地は国内では九十九里浜から鹿島灘(千葉~茨城)や、三重県桑名などが有名です。産卵前の3~4月ごろが旬と言われ、潮干狩りシーズンと重なるのも特徴的です。桃の節句のひな祭りには、ハマグリのお吸い物が欠かせない存在。貝殻がぴったり合うのは一対のみなので、夫婦仲が良い象徴とされている点も興味深いでしょう。
フキノトウ
フキがまだ芽の状態の時期に収穫されるフキノトウは、雪の下からも顔を出す早春の味覚です。川沿いや湿り気のある斜面でよく見られ、芳香とわずかな苦みが魅力。天ぷらやフキみそにして食べるのが定番です。春に苦味を食すると体に良いと昔から言われており、自然の恵みを感じる山菜と言えます。
桜エビ
体長4cmほどの透明感ある淡いピンク色をした深海エビです。日本では静岡県の駿河湾だけで漁が許可され、年間2回の漁期(春と秋)が設定されています。春は3月中旬から漁が始まり、かき揚げなどで甘みと香ばしさを同時に楽しむ人が多いようです。殻や内臓ごと丸ごと食べられるため、下処理が不要なのも魅力。駿河湾沿いの漁港に足を運べば、サクサクのかき揚げを味わうことができます。
春の果物
イチゴ

ハウス栽培の普及により、冬場から出回るイチゴですが、本来の露地栽培では3~4月が旬です。春イチゴは、しっかりと熟して甘みが強いのが特徴と言われています。
大粒で白い「天使の実」(佐賀県産)、内部まで赤く糖度の高い「真紅の美鈴」(千葉県産)、誕生間もない新品種「よつぼし」(三重県など)など、国内には300以上の品種があり、年々新種が増え続けているのも面白いところです。
伊予柑
温州みかんに次ぎ生産量が多い柑橘類が伊予柑です。冬を越えた3月ごろに収穫されることもあり、糖度が高まった「弥生紅(やよいべに)」と呼ばれる愛媛産が有名。酸味が控えめで爽やかな香りを持ち、手で簡単に皮がむけるのも人気の理由です。
夏みかん
「夏みかん」の名称とは裏腹に、実は春が旬。秋に実がなった後、追熟期間を経て酸味を落とすことで4~5月に美味しい状態になります。江戸時代中期に海外から種子が流れてきた説などもあり、見た目以上に歴史ある柑橘と言えるでしょう。
キウイフルーツ
熱帯風の印象ですが、キウイフルーツの需要が高まるのは3月ごろ。国産は秋~冬に収穫して貯蔵し、追熟期間を経たうえで春先に多く出回るためといわれます。ヨーグルトとの相性が抜群で、酸味を和らげる形でのスイーツやケーキなどにもアレンジ可能。手軽に栄養補給できるのも利点でしょう。
春の食材を使った料理
天ぷら・揚げ物

春に出回る山菜や苦みのある食材を揚げると、風味が穏やかになるのでうまくバランスが取れます。タラの芽やフキノトウは苦味がやや強い印象ですが、衣をまとって揚げればほんのりとした香りが引き立ち、春の味わいを存分に堪能できると言えるでしょう。
さらに素材の持ち味をしっかり味わうには、塩にもこだわると楽しいものです。岩塩・海水塩・藻塩など産地によって成分や舌触りが変わり、天ぷらには粒子の細かいタイプが相性が良いとされています。塩のバリエーションを試すことで、より奥深い春の食卓に仕上がるのではないでしょうか。
寿司・ちらし寿司
菜の花やさやえんどうなど、色鮮やかな素材でちらし寿司やばら寿司を作る家庭も多いようです。春を象徴する一皿として、見た目だけでなく味でも季節を楽しめるのが嬉しいところです。
もっと春らしさを満喫したいなら、手まり寿司も好評です。菜の花や卵、サーモンや桜えびを組み合わせれば、彩りが一段と映えますし食べやすさもアップ。特にお子さんと一緒に作れば、パーティー感覚で盛り上がるかもしれません。
まぜご飯・炊き込みご飯

春にはたけのこやごぼう、アサリやシラスなどお米とよく合う食材が次々と登場します。こうした素材を使ったまぜご飯や炊き込みご飯は、手軽に季節感をプラスできるのが魅力でしょう。
いつもの和風炊き込みご飯を変化させたいなら、洋風アレンジの「パエリア」もアリです。春野菜や魚介のうまみがお米にしっかり溶け込み、見た目も香りも華やかに仕上がると思います。こうした調理方法を取り入れて、季節を丸ごと味わってみてはいかがでしょうか。
春の花
桜

日本の春といえば桜。その代表格であるソメイヨシノだけでなく、国内には600種以上が存在します。元は11種(または10種)の野生種から生まれた自然交配や人工交配によるものだとか。1955年に静岡県で発見された「河津桜」は花期が早く、全国から観光客が訪れる人気スポットになっています。青森・弘前城の花筏や、北海道でのGWに咲く桜など、開花時期が地域ごとに異なるため、春が長く楽しめるのも桜の特長です。
菜の花

開花時期は3月~4月あたりが中心で、広い一面を黄色に染める風景が絶景として人々を魅了します。アブラナ科の植物には高菜やからし菜など多様な品種が含まれ、畑や種類によって花の時期が微妙に異なるようです。宮城県角田市、埼玉県幸手市の権現堂桜堤、岡山県総社市の備中国分寺など、春限定の絶景を楽しめる名所が各地に存在します。
チューリップ
まるみを帯びた形状が愛らしいチューリップは、日本国内でも非常に親しまれています。江戸時代後期に伝来したと考えられており、今では国内の主要産地が富山県と新潟県となっています。中でも富山県は国内最大の球根生産を担い、砺波チューリップ公園で行われる「となみチューリップフェア」は四月下旬から五月上旬にかけて開かれています。
桃
「桃」は弥生時代に栽培が始まり、当初は観賞目的だったようです。古文献の『古事記』や『日本書紀』にも登場し、桃には厄を祓う力があると信じられていました。さらに、桃から誕生した主人公が犬・キジ・サルを従えて鬼退治をする「ももたろう」は、子どもにとっての代表的な民話です。日本国内では福島県や山梨県が産地として有名です。
藤

「藤」も昔から、その淡い紫色の花房が垂れ下がる美しさで多くの人を魅了してきました。女性の優雅さをたとえる場面でも用いられ、日本舞踊においては藤の花の精が舞う「藤娘」という演目が有名です。開花時期は四月中旬から五月上旬で、つる性をいかした藤棚の光景が全国各地に広がっています。
ボタン(牡丹)
「おはぎ」を春に食べると「ぼたもち」と呼ぶのは、牡丹の花が咲くシーズンであることに由来すると言われます。4月ごろに見ごろを迎え、大輪で優雅な姿は「百花の王」という別名にも納得できるほど。神社や寺院のモチーフ、着物や工芸品の柄など、伝統文化でも親しまれています。
春の七草
1月7日に食べる七草粥や1月15日の小正月など、地域によって時期はさまざまですが、せり・なずな・ごぎょう・はこべら・ほとけのざ・すずな・すずしろを組み合わせた七草粥は春の風物詩の代表例です。ビタミン不足解消にも役立ち、昔から無病息災を願って食されてきました。
春のイベント・行事
お花見

日本人に深く愛される桜。その満開の美しさを楽しむ「お花見」は、桜を眺めながら穏やかなひとときを過ごす行為を意味します。家族や仲間と飲食を楽しみながら桜の下で語り合う、この独特の慣習は多くの人に親しまれていると言えるでしょう。花見の名所としては、東京の上野公園などが特に有名です。
桜祭り
これは桜鑑賞をお祭りとして行う形態で、多くの観光客を呼び寄せる行事でもあります。桜が密集する公園など、日本各地で実施されている点が特徴でしょう。たとえば、日本三大桜名所のひとつに挙げられる弘前公園(青森県)で催される「弘前さくらまつり」には、国内外から約二百万もの来場者があるようです。
潮干狩り

春先から初夏にかけて、潮が引いた砂浜でアサリなどを収穫するアウトドア体験を指します。家族連れに大変喜ばれ、宝探しのような楽しさとともに、その場で新鮮な貝を味わえる機会でもあるでしょう。
ひなまつり
3月3日は桃の節句で、女の子の健やかな成長を願うひなまつりが開催されます。立春を迎えた2月上旬から雛人形を飾る家庭も多く、当日はちらし寿司やハマグリのお吸い物、ひし餅などを用意して祝うのが一般的です。ひな人形を片付ける時期については諸説ありますが、天気や湿度の条件が良い日に収納するのがトラブルを防ぐコツとされています。
梅まつり・菜の花まつり
桜より少し早めに満開を迎える梅や、一面が黄色に染まる菜の花など、各地で季節を祝う祭りが催されます。ご当地限定の屋台グルメや特産品販売も魅力。
卒業式・入学式
春は出会いと別れの季節。日本では4月を年度の始まりとするため、卒業式が3月中旬、入学式が4月上旬に行われるケースが多いです。桜の開花時期と重なることもあり、門出を祝うムードで街が包まれるのがこの季節の特徴と言えるでしょう。
エイプリルフール
4月1日はウソを言っていい日、という風習が欧米から伝わり、今では国内の企業や報道機関がSNSでジョークやフェイクニュースを投稿することも珍しくありません。午前中だけが本当のエイプリルフールタイムという説もあるようで、人を傷つけない遊び心あるウソなら大歓迎といったところでしょうか。
ホワイトデー
バレンタインデーにチョコやプレゼントをもらった人が、お返しをする日がホワイトデーです。マシュマロやキャンディーが定番だった時期もありますが、今では多様なお菓子や雑貨が選ばれています。日本独自の文化が広まった例としては面白い存在と言えます。
春を楽しむための便利アイテム
お花見や桜祭り、潮干狩りなど、屋外で過ごすイベントが多い春。そんな春の行楽をより楽しむためには、ポータブル電源がおすすめです。春のどんなシーンで、ポータブル電源が活躍してくれるのか見てみましょう。
お花見や桜祭りなら
お花見の醍醐味の一つは食事ですよね。ポータブル電源があれば、みんなで持ち寄った食事を温めたり、みんなで軽食を調理したりと楽しみが広がります。大人数でもみんなのスマートフォンやカメラのバッテリーを充電できるので、長い宴会にも最適です。
潮干狩りなら
まだ涼しい春といっても、潮干狩りは喉が渇きます。ポータブル電源があれば、ミニ冷蔵庫でキンキンに冷やした飲み物でリフレッシュできたり、採れたてのアサリを調理して味わうことだって可能に。頑張って疲れた体に癒しが得られること間違いなしです。
おすすめポータブル電源① AORA80

日本限定 ポータブル電源「AORA 80」 は、日本ユーザーの声を元に、機能性、携帯性、安心感を追求したモデルです。シンプルで洗練されたフォレストグリーン色合いの外観は、おしゃれなライフスタイルにもピッタリ。容量768Whと大容量なので、スマホやカメラは45回、GoProやドローンなら29.4回の充電ができ、春の行楽シーズンにうってつけの一台です。
-
春の行楽におすすめの理由
-
携帯電話、小型スピーカー、魔法瓶をいつでも充電できるので、春の屋外でのお出かけをより快適に過ごすことができます。
-
芝生でのピクニックやビーチでのパーティーでも、AORA80はポータブル冷蔵庫、調理器具、照明に継続的な電力サポートを提供し、あらゆる瞬間を笑いと便利さで満たします。
-
BLUETTI Charger 1と一緒に使えば、1.8 - 2時間のドライブでフル充電が可能。
AORA80を持って、桜の木の下で家族や友人と暖かい時間を共有しましょう。
おすすめポータブル電源② BLUETTI Charger 1
BLUETTI Charger 1は、コンパクトながら車のオルタネーターから電力を取り出せる仕組みを備えており、車での外出に最適!目的地へ向かうドライブ中に充電しておけば、アウトドアでの電力不足を回避でき、春に重宝するアイテムと言えます。
-
春の行楽におすすめの理由
-
車のバッテリーやオルタネーターと連携するため、行楽の行き道でその日の電源を確保できる。
-
持ち運びしやすいサイズ感と設計で、行楽やキャンプ、万が一の緊急時にも活躍の場が多い。
-
大容量バッテリーを組み合わせれば、スマートフォンやタブレット、カメラなど複数の機器を同時に充電可能。
-
AORA80と組み合わせれば、1.8 - 2時間のドライブでAORA80をフル充電。
まとめ
春は入学や就職など環境の変化が大きい季節ですが、一方で食べ物・花・行楽など多面的に楽しめるイベントも満載です。いちご狩りや潮干狩り、桜や菜の花の名所めぐりなど、暖かくなり始めるタイミングを逃さず、自然や文化に触れる時間を積極的に作ってみましょう。
ご家族や友人と楽しい思い出を残すなら、写真やビデオを撮り続けられるようにポータブル電源があると良いです。電子機器や調理家電を動かせれば、お花見も行楽ももっと楽しくなること間違いなし。今年の春は四季がはっきりしている日本ならではの「春の風物詩」を存分に味わいながら、新年度や新生活を爽やかにスタートさせてはいかがでしょうか。