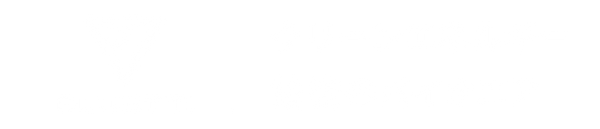「地震で震度8ってあるの?」そんな疑問をお持ちの方も多いでしょう。この記事では最大震度とその理由、マグニチュードとの違いを解説します。さらに発生が懸念される南海トラフ巨大地震への備えや防災対策のポイントをまとめました。最後まで読めば災害リスクへの理解が深まり、命を守るうえで知っておきたい地震の知識を手に入れられるでしょう。
結論、最大震度は7。「震度8」や「震度10」は必要か?
最大震度は「7」なのか「10」なのか、あなたは最大震度を正しく理解しているでしょうか。株式会社エコンテ(東京都渋谷区)が20歳以上の男女500名に実施したアンケート(2016年)では、最大震度の正答率はおよそ50%だそう。約半分の日本人は最大震度を間違えて覚えてしまっているのです。結論としては、日本の気象庁が定める震度階級は震度0から震度7までとなっており、これが事実上の最大値です。
半分の日本人が「震度8」があると思っている理由とは?
前述の通り、日本の震度階級の中で最大震度は「7」が最大値です。しかし、気象庁が定める震度階級は、「震度0」「震度1」「震度2」「震度3」「震度4」「震度5弱」「震度5強」「震度6弱」「震度6強」「震度7」の10段階となっています。この「震度=10段階」という認識がひとり歩きして「震度10」や「震度8」があると考える人が増えているのです。
震度8や震度10が存在しない2つの理由
「震度7を超えるほどのすさまじい揺れがあるのなら、震度8や震度10を設定してもいいのでは?」と感じるかもしれません。けれども技術的な観点と実用性の観点から、最大震度は7と決められているのです。
1つ目の理由は、「震度の計測限界」という技術的な問題。計測震度計の上限をはるかに超えるほどの激しい揺れは、統計的にも珍しく、かつ判定不能な領域に近いです。震度7を観測するような大地震でも、観測点の位置や地盤によってはすでに計測器の飽和点に達しかねません。そこからさらに揺れが激しくなったかどうかを正確に測定するのは困難と言われています。
2つ目の理由は、「情報の実用性と分かりやすさ」。もし震度8や震度10などを導入してしまうと、緊急放送や速報での扱いが煩雑になり、国民がパニックを起こす可能性があります。特に防災情報は即座に共有されるため、階級が増えすぎると混乱を招きかねません。震度7という最大階級を設定することで、「これ以上に揺れが大きい場合は、もはや区別の必要もないほどの壊滅的レベル」という明確なラインを引いているのです。
したがって、日本の震度としては「7が最大」という認識が公式のルールとして定着しています。
一方で海外の一部機関などでは、震度の考え方が日本と異なり、震度階級が10段階や12段階まである例も見受けられます。ただし、それは各国の測定基準や表記方法の違いによるものです。結果として、日本においては「震度7が最大」というシンプルな定義が実用的だと広く認識されています。
それでも、世間で「震度8」や「震度10」などの表現を耳にした場合、それは単純に「非常に強い揺れ」というイメージを誇張的に表す通称であるケースが多いようです。少なくとも公式の震度階級としては存在しません。
震度が意味することとは?気象庁が採用する震度基準と揺れ方の目安
日本の地震情報を語るうえで欠かせないのが、気象庁が定める震度階級です。これは全国共通の基準として用いられており、現在は主に震度0~7までの10段階(1、2、3、4、5弱、5強、6弱、6強、7)に区分されます。震度の発表基準にはかなり細かいルールが存在し、それを支えているのが「計測震度計」です。
震度情報は、テレビやラジオ、SNSを通じて瞬時に全国へ広がるため、日常的に耳にする大切な情報源といえます。具体的な計測方法や震度階級がどう定義されているかを解説していきましょう。
地面の揺れを正確に捉える「計測震度計」の役割

出展:明星電気株式会社ホームページ
震度は単なる主観的な「揺れの感じ方」ではなく、「計測震度計」という機器によって定量的に測定されるのが特徴です。従来は人間の感覚や建物の被害状況などを含め、ある程度主観的に震度を決定していた歴史がありました。しかし1996年から導入された計測震度計により、地盤や建物などの要素を含めた揺れの強さを物理量で測れるようになっています。
この計測震度計は、加速度センサーによって地面の揺れを捉え、コンピューターが適切な換算式を使って震度として算出します。例えば加速度が一定の閾値を超えれば震度5弱、さらに強ければ5強、6弱、6強…と段階的に上がっていく仕組みです。感覚や建物被害に依存せず、数値的な基準で判断されるため、公平性と再現性が高いといわれています。
なお、地面の硬さや地盤の性質によって同じ地震でも揺れ方は大きく変わります。都市部の埋め立て地などは揺れが増幅される傾向にあり、岩盤の固い地域よりも大きな震度を観測する場合があるのです。そのため、震源に近くても地盤が固ければ震度が小さくなるケースもあります。
震度ランク別に見る揺れの度合い
現在、日本の震度階級は以下のように分かれています。
|
震度 |
体感・被害の目安 |
|
0 |
人間は揺れを感じない。計測器は記録する場合がある。 |
|
1 |
室内にいても揺れをわずかに感じる程度。 |
|
2 |
室内にいる人の多くが揺れを感じるが、物が落ちるほどではない。 |
|
3 |
戸や窓がカタカタ鳴る程度。吊り下げ物がわずかに揺れる。 |
|
4 |
食器棚の食器が音を立てる。棚の上のものが落ちることがある。 |
|
5弱 |
固定していない家具が倒れ始める。人によっては行動に支障をきたす。 |
|
5強 |
棚が倒れたり、固定していないテレビが落下したりする。揺れが非常に強い。 |
|
6弱 |
立って動くことが困難。大きな家具が大きく移動または倒壊する。 |
|
6強 |
建物の壁にひび割れが生じたり、瓦が落ちるなどの被害が発生しやすい。 |
|
7 |
「建物が大規模に損壊する」レベルの極めて強い揺れが想定される。 |

出展:気象庁ホームページ
上の表で示した通り、震度7は「建物が大規模に損壊する」ほどの強い揺れが想定される段階です。震度7は、熊本地震や東日本大震災でも観測されましたが、その破壊力は想像を絶するレベルです。
5弱~5強あたりから家具が倒れるなどの物的被害が急増し、6弱~6強になると建物の一部損壊が顕在化します。そして7に至ると、耐震性が十分でない建物では倒壊が起こりうるという認識でよいでしょう。これが「震度7を超えるほどの揺れは、区別する意味があまりない」とされる主な理由にもつながります。
震度とマグニチュードはどう違う?—「揺れの強さ」と「地震規模」の差

地震を語るとき、震度と同じくらいよく耳にするのが「マグニチュード(M)」です。ただし、この2つは全く異なる概念なので注意が必要です。
-
震度:ある地点で観測された揺れの強さ
-
マグニチュード:地震そのもののエネルギー量
震度が「どこでどれだけ揺れたか」を示すのに対し、マグニチュードは「地震の規模がどれほど大きいか」を示す指標です。例えば、マグニチュード9.0の超巨大地震であっても、震源から遠い地域では震度3程度しか観測されないことがあり得ます。逆に、マグニチュードが小さくても、震源が浅くて真下に位置する地域では震度5強や6弱になるケースが存在するわけです。
よくニュースなどで「今回の地震はマグニチュード◯.◯でした」という報道を耳にすると思いますが、それだけではあなたがいる場所の揺れがどれほど強かったのかは分かりません。あくまで地震の“規模”なので、詳しく知りたいときは震度情報もあわせてチェックしましょう。
南海トラフ巨大地震が発生したら、最大震度はどうなる?

出展:NHKニュース
次に、今最も警戒されている南海トラフ巨大地震について触れたいと思います。南海トラフ巨大地震とは、駿河湾から四国沖を通って九州沖に至る南海トラフで発生が予想される超巨大地震のことです。マグニチュードは8~9クラスになると想定されており、被害が広範囲に及ぶ可能性が高いと指摘されています。
静岡から宮崎まで、広域的に震度6~7が予測される深刻な地震に
南海トラフ巨大地震が起きた場合、「静岡県から宮崎県までの太平洋沿岸部を中心に、震度6弱から7に達する激しい揺れが想定される」と報道されています。特に沿岸部は地形によって揺れが増幅される地点が多く、倒壊や大規模な火災のリスクが高まることが懸念されています。
さらに、各自治体の防災情報からも分かるように、古い建築基準で建てられた家屋では大きな被害が発生する恐れがあります。耐震補強や家具の固定などを含め、防災対策をしっかり進めることが大切です。
今後30年以内に70~80%の確率で発生するとされる根拠
南海トラフ巨大地震は、政府の地震調査委員会によれば、「今後30年以内に70~80%の確率で起こる」と試算されています。これは非常に高い確率で、今生きている世代が直面する可能性がきわめて高い災害ということです。
この確率はあくまでも統計モデルに基づく計算ですが、歴史的な南海トラフ沿いの大地震の発生間隔や地殻変動の観測結果など、多角的な観点から推定されています。
こうした状況を考えると、早い段階での備えが求められるのは当然かもしれません。特に、大きな地震が来たときに倒れやすい家具や食器棚、テレビなどをしっかり固定しておくなど、物理的な被害を最小限に抑える努力が欠かせません。
10m超の津波で32万人超の死者も想定される危険シナリオ
さらに深刻なのが津波被害の予測です。南海トラフ巨大地震では、最悪の場合10m以上の津波が沿岸部を襲い、約32万人以上が亡くなるシナリオが示唆されているともいわれます。これは阪神・淡路大震災や東日本大震災以上の犠牲者数に及ぶ可能性があります。
津波被害を減らすためには、とにかく早く高台へ逃げることが最も重要です。地域の避難所の場所や避難ルートの確認、そして日頃の避難訓練の参加なども意識しておきたいところです。海岸に近い地域にお住まいの方は、行政が公表している津波ハザードマップを活用し、避難場所や経路を事前にシミュレーションしておきましょう。
かつて観測された「震度7」の地震事例—過去の最大級の揺れを知る

過去に震度7を記録した地震はいくつかあります。近年の事例を取り上げることで、「震度7クラスの揺れ」がどれだけ甚大な被害をもたらすかを具体的にイメージできるはずです。以下、主な例を挙げます。
1. 2024年 能登半島地震
-
最大震度:7(石川県能登地方)
-
2024年に石川県能登地方で発生した地震では、珠洲市を中心に大規模な建物損壊と長期間の停電が報告されました。海岸付近では地盤沈下も見られ、漁業や観光業への打撃が懸念されるなど、地域経済に大きな影響を与えています。
2. 2016年 熊本地震 2011年 東日本大震災
-
最大震度:7(前震・本震ともに観測)
-
熊本県益城町などを中心に、短期間で2回の震度7が発生し大混乱に陥りました。家屋の倒壊や道路の亀裂などが重なり、地盤の緩みによる土砂崩れも各地で相次いだことが被害拡大の要因とされています。
3. 2011年 東日本大震災
-
最大震度:7(宮城県など)
-
マグニチュード9.0という国内観測史上最大級の規模で、太平洋岸一帯に未曾有の被害をもたらしました。震度7を記録した地域では、津波や原子力発電所事故による二次災害が連鎖し、被害は一気に全国規模へ拡大。広範な地域で長期間の避難生活を強いられる事態に発展しています。
4. 1995年 兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)
-
最大震度:7(淡路島・神戸市など)
-
都市部を直撃し、高架高速道路の崩落や大規模火災が発生。木造住宅の密集地域を中心に倒壊が相次ぎ、神戸市内は深刻な交通・物流麻痺に陥りました。復旧に長い期間を要したのが特徴的です。
より強固な対策が必須。高震度の揺れに脆い建物や地域とは?
地震が起きると、建物被害や地盤の影響が如実に現れます。ここでは、どのような建物や地域が特に脆弱なのか、4つのポイントに分けて見ていきましょう。
古い木造住宅

昭和56年以前に建てられた古い木造住宅は、耐震性が不十分である可能性が高いです。新耐震基準が導入される前の建築物では、設計時に想定される揺れの規模が小さく設定されていたため、大きな地震に耐えられないリスクが上昇します。耐震補強やリフォームを検討する際は、行政の助成金制度などのサポートも活用してみてください。
軟弱地盤の上の建物
埋め立て地や川沿いなどの軟弱地盤に建つ建物は、揺れが増幅しやすく液状化リスクも高まるため注意が必要です。液状化による地盤の沈下や建物の傾きが発生すると、建物全体の耐久性が損なわれる可能性があります。地盤改良工事や免震構造の建物を選ぶなどの対策を検討すると安心です。
急斜面の近く
急斜面の麓や山間部に位置する住宅は、地震による土砂崩れやがけ崩れに巻き込まれるリスクが高いといえます。特に降雨量の多い地域では、地震と豪雨が重なることで土砂災害の危険性が一層増すことも。近隣に大きな崖や斜面がある場合は、ハザードマップの確認や早めの避難経路の確保が大切です。
高層ビルの高層階
都市部の高層ビルやマンションでは、長周期地震動によって上層階が大きく揺れる現象が懸念されます。建物が倒壊することは少なくても、家具の転倒や室内の散乱など生活空間へのダメージが大きくなりやすい点に注意が必要です。上層階に住む場合は、家具固定や防災グッズの準備をより念入りに行っておきましょう。
こうした建物や地域に該当する方は、早めの耐震診断や補強工事、そして避難ルートの確認など、リスク低減のための対策を検討してみてください。備えがあれば、いざというときに被害を最小限に抑えられる可能性が高まります。
家庭で取り組む地震への備え
大きな地震がいつやって来るかは誰にも正確には分かりません。しかし、いつかは必ず来るものだと想定して準備をしておくことで、被害を最小限に抑えることができます。ここでは家庭で取り組める具体的な防災対策を紹介します。
非常袋に入れるべき基本アイテム(食料・水など)
まず基本となるのが防災グッズです。「最低7日分の食料・水は必ず確保しておく」ことが推奨されています。災害時にはライフラインが途絶えやすく、コンビニやスーパーも営業停止に陥る可能性があります。普段からレトルト食品や缶詰、水のペットボトルなどをローリングストック方式で備蓄しておけば、いざという時に慌てずに済むでしょう。
医薬品も忘れずに備蓄する
医薬品も大切な備えです。常備薬や救急セット、絆創膏、消毒液などをまとめて1つの防災バッグに入れておくとスムーズに持ち出せます。体質的に特別な医薬品が必要な方は、必ず忘れずに準備してください。災害時は通常の医療体制が整わないことも多いため、十分な量をストックしておくと安心です。
備蓄の新常識:ポータブル電源を準備する
そして近年注目を集めているのがポータブル電源です。大地震で停電になると、照明やスマホの充電、簡易的な家電の使用などが困難となりますが、ポータブル電源があれば、電気ポットや電気毛布といった家電も使える可能性があり、寒さや空腹をしのぐことができます。容量や出力の異なる製品が多いため、家庭の必要に合わせて選び、もしもの時に備えておきましょう。ソーラーパネルと組み合わせれば外部電力に頼らない独立電源としても期待できます。
いざという時に役立つポータブル電源のおすすめ
災害対策の新常識とされているのが、大地震や停電時の強い味方となるポータブル電源です。停電時には、スマホによる災害情報の収集や安否確認が重要です。SNSやWebニュースなどリアルタイムで情報を得られる手段があるのは心強いものの、電源が切れてしまえばそれまで。非常用電源としてポータブル電源を備えるメリットは計り知れないでしょう。防災リュックや非常食と同じくらい、「あってよかった」と心から思えるアイテムになるでしょう。ここではおすすめの製品を2つご紹介します。
BLUETTI AORA 100 大容量ポータブル電源 | 防災推奨 |1152Wh、1800W
日本語表示の画面とポート、ボタンにより、初心者でも直感的に操作でき、幅広い年齢層に優しい設計です。地震や台風などの災害の際、AORA 100のUPS機能は停電をわずか20msで感知し、内部バッテリーから電源供給を開始します。長期間の停電でもスマートフォンを最大18日間、電力供給できるので安心。Charger 1を使えば、車で避難する間に500Wで充電可能。ソーラーチャージも可能で、避難所でも太陽光を電力に変換してためておく事ができます。
BLUETTI Charger 1 | 560W オルタネーターDC充電器
ポータブル電源を持っている場合でも、予備の充電手段を用意しておくことが重要です。マイカーが地震に耐えた場合、Charger 1を使えば車のオルタネーターからの余剰電力を用いてポータブル電源を素早く充電し、他の必要な機械にバックアップ電源を供給することができます。たとえ広範囲な停電が続いていても、自動車を利用できる状況なら電力を確保できることが特徴。夜間や悪天候でソーラーパネル充電が使いにくい場合にも対応しやすいため、非常時における充電手段の多角化が期待できます。
まとめ
ここまで、最大震度が7とされる理由や南海トラフの危険性、そして家庭での対策などを詳しく見てきました。高震度の揺れはいつ発生しても不思議ではありませんが、備えこそがあなたと大切な人を守るための第一歩です。この記事を機に、防災グッズやポータブル電源の準備、住まいの耐震見直しなど、できることから一つずつ始めてみましょう。小さな行動の積み重ねが、非常時に大きな安心をもたらします。