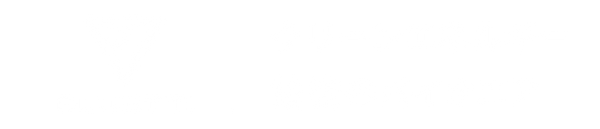本記事では、世界の地震が多い国ランキングや、過去に大きな規模で起きた地震の事例、そして日本独自の防災文化や地震対策を含む多角的な情報をまとめました。さらに、万が一のときに備えて今から行うべき防災対策についても詳しくご紹介します。
地震は突発的に起こるだけでなく、私たちの生活基盤を根本から揺るがすものです。備えあれば憂いなしという言葉があるように、本記事を読んで必要な情報を手に入れてください。
世界中で地震が多発している国は?ランキング上位10か国を徹底チェック

世界各地には、プレートの境界など地殻の活動が活発な地域が多数存在します。特に環太平洋火山帯や、ユーラシア大陸とアフリカ大陸の境界付近は地震活動が盛んなことで知られています。国際機関や各国の防災機関の統計をもとに算出されたデータによると、「被害額が100万ドル以上、死者10人以上、マグニチュード7.5以上、もしくは津波を伴う」いずれかの条件を満たした地震を観測した回数が多いランキングは以下の通りです。
|
順位 |
国名 |
主要地震の発生件数 (1990~2024) |
|
1 |
中国 |
186 |
|
2 |
インドネシア |
166 |
|
3 |
イラン |
109 |
|
4 |
日本 |
98 |
|
5 |
アメリカ合衆国 |
78 |
|
6 |
トルコ |
62 |
|
7 |
インド |
58 |
|
8 |
フィリピン |
55 |
出典:NOAA (2024年1月2日時点の推計)
ランキングでは中国が1位となっていますが、これは国土の広さやチベット高原・四川盆地など内陸部でも大きな地震が起こりやすい地形的要因が関係しているからです。インドネシアは環太平洋火山帯に属し、火山活動や海溝型地震が頻繁に起こるため2位。イランやトルコなど中東から中央アジアにかけては、複数のプレートが交わる地域のためマグニチュードの大きい地震がたびたび発生していると考えられています。
そして注目すべきは4位の日本。島国である日本列島は、ユーラシア、北米、太平洋、フィリピン海と4つのプレートが複雑にせめぎ合う場所に位置しているため、比較的小さな国土面積ながらたびたび大きな地震に見舞われてきました。後述するように日本では地震に対する耐震技術や建築基準、さらに住民の防災意識が高いため、地震発生回数の多さのわりには被害を抑制している面があります。しかし津波や火災など、二次災害のリスクを考慮すると油断は禁物だといえるでしょう。
規模・被害にも要注目!その他の地震関連ランキングまとめ
地震が多く発生する国を把握したうえで、次に重要なのは「どのような規模の地震がどれほどの被害をもたらしているのか」という点です。地震の大きさを示す代表的な指標としてはマグニチュード(Mw)が挙げられますが、実際には震源の深さ、震度、周辺の人口密度、建物の耐震性などにより被害は大きく左右されます。ここでは地震の規模ランキングや被害ランキング、経済的なダメージを与えた地震の例を見ながら、地震の多面性について理解を深めてみましょう。
地震の規模ランキング(1900年以降に発生した地震の規模の大きなもの上位10位)
地震の規模そのものを示すのがマグニチュードで、Mが0.2上がるごとに地震のエネルギーは2倍ほど増すとされています。1900年以降に発生した主な巨大地震のマグニチュード上位10位を以下にまとめます(日本時間)。
|
順位 |
日時(日本時間) |
発生場所 |
マグニチュード(Mw) |
|
1位 |
1960年5月23日 |
チリ |
9.5 |
|
2位 |
1964年3月28日 |
アラスカ湾 |
9.2 |
|
3位 |
2004年12月26日 |
インドネシア、スマトラ島北部西方沖 |
9.1 |
|
4位 |
2011年3月11日 |
日本、三陸沖「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」 |
9.0 |
|
5位 |
1952年11月5日 |
カムチャッカ半島 |
9.0 |
|
6位 |
2010年2月27日 |
チリ、マウレ沖 |
8.8 |
|
7位 |
1906年2月1日 |
エクアドル沖 |
8.8 |
|
8位 |
1965年2月4日 |
アラスカ、アリューシャン列島 |
8.7 |
|
9位 |
1950年8月15日 |
チベット、アッサム |
8.6 |
|
10位 |
2012年4月11日 |
インドネシア、スマトラ島北部西方沖 |
8.6 |
|
10位 |
2005年3月29日 |
インドネシア、スマトラ島北部 |
8.6 |
|
10位 |
1957年3月9日 |
アラスカ、アリューシャン列島 |
8.6 |
|
10位 |
1946年4月1日 |
アラスカ、アリューシャン列島 |
8.6 |
このように、歴史的に見て最大規模だったのは1960年のチリ地震(M9.5)。津波が太平洋沿岸を襲い、ハワイや日本にも大きな被害をもたらしました。インドネシア・スマトラ島沖もM9.1やM8.6以上の地震が立て続けに起こっているのが特徴で、ここでは海底のプレートが大きくずれ動いて巨大津波を誘発し、広範囲で甚大な被害を生じています。
特に日本の東北地方太平洋沖地震(2011年)は、歴史上4番目の規模として記憶される大災害になりました。マグニチュード9.0という非常に大きなエネルギーが放出され、津波や原発事故のリスクなど、さまざまな複合的被害をもたらした点でも国際社会に大きな影響を与えた地震です。
人命被害の大きさから見る地震ワーストランキング
地震の被害はマグニチュードの大きさだけでなく、震源の浅さ、人口密度、建築物の耐久性などに大きく左右されます。以下に、地震の被害ランキングを表形式でまとめました。(※死者・行方不明者数はいずれも概数です)
|
順位 |
地震名 |
発生日 |
死者・行方不明者数 |
|
1 |
唐山地震 |
1976年7月28日 |
242,000 |
|
2 |
スマトラ島沖地震 |
2004年12月26日 |
226,000 |
|
3 |
ハイチ地震 |
2010年1月12日 |
222,600 |
|
4 |
海原地震 |
1920年12月16日 |
180,000 |
|
5 |
アシガバート地震 |
1948年10月6日 |
110,000 |
|
6 |
関東大震災 |
1923年9月1日 |
143,000 |
|
7 |
四川地震 |
2008年5月12日 |
87,500 |
|
8 |
メッシーナ地震 |
1908年12月28日 |
75,000 |
|
9 |
甘粛地震 |
1932年12月25日 |
70,000 |
|
10 |
アンカシュ地震 |
1970年5月31日 |
70,000 |
当時の記録によれば、唐山地震では24万人以上の方が犠牲になったと推計されています。こうした歴史的大災害から分かるように、人口の集中度合いや建物の耐震性能がまだ十分でなかった時代ほど、被害が拡大しやすい傾向にあります。
一方、2004年のスマトラ島沖地震は規模がM9.1と極めて大きかったうえ、沿岸部で発生した巨大津波がマレーシア、タイ、インド、スリランカ、東アフリカ諸国にまで広範囲に到達し、大きな人的被害をもたらしました。また日本の関東大震災(1923年)はマグニチュード7.9と上記のランキングほどの大きさではありませんが、首都圏で発生し、火災をはじめとする二次災害も重なって甚大な打撃を受けました。
経済的な被害の大きさから見る地震ワーストランキング
経済的な被害額は、国や地域のGDP規模、インフラの集中度合いなどによっても大きく変動します。以下は、1980年以降の地震による経済的被害額が大きい上位5つをまとめた表です。金額は2011年の物価換算をベースにしており、死者数も参考として記載しています。
|
順位 |
地震名 |
発生年 |
経済的損失 (2011年価格ベース) |
死者数 |
|
1 |
東日本大震災(日本) |
2011年 |
2,100億ドル(約16.8兆円) |
15,840人 |
|
2 |
阪神・淡路大震災(日本) |
1995年 |
1,480億ドル(約11.8兆円) |
6,430人 |
|
3 |
四川大地震(中国) |
2008年 |
890億ドル(約7.1兆円) |
84,000人 |
|
4 |
ロサンゼルス地震(米国) |
1994年 |
670億ドル(約5.4兆円) |
61人 |
|
5 |
新潟県中越地震(日本) |
2004年 |
330億ドル(約2.6兆円) |
46人 |
なんと上位5位のうち、3つが日本の地震となっているのです。さらには1位、2位と上位を独占してしまっています。震度の大きさに加え、都市部のインフラや産業集積地帯が被災すると復興費用が天文学的に膨れ上がります。特に2011年の東日本大震災は津波によって東北地方の漁業や農業が大打撃を受け、原発事故の影響も含めて経済・社会に甚大なダメージが残ったのが大きな特徴です。阪神・淡路大震災(M7.3)も震源が都市部に近かったことで経済面の被害が莫大でした。
世界4位の地震大国・日本、その犠牲と損失は想像以上に深刻!
前述の「地震が多い国ランキング」でも示されたように、日本は世界第4位の地震発生回数を抱えています。プレートの境目が集まる地理的な宿命であり、近年だけでも能登半島地震(2024年)や熊本地震(2016年)東日本大震災(2011年)など大規模な地震が起きています。
日本の歴史を振り返ると、地震のたびに多くの建物やライフラインが被害を受け、さらには津波や土砂災害など二次災害による多大な損失が発生してきたのが現実です。被害額だけでなく、尊い人命を奪われるという損失は計り知れません。ただ、そのたびに耐震基準が強化され、防災教育が進められてきたことで、近年の新築物件や公共施設は倒壊しにくい構造へと大きく進化しています。
日本が築いてきた地震対策
日本は歴史的に何度も大きな地震や津波被害を経験してきましたが、その度に技術革新や制度の強化を積み重ねてきました。具体的には、建築基準法の改正や津波警報システムの整備、学校における避難訓練の徹底など、多岐にわたります。
歴史に裏打ちされた日本独自の地震対策と文化
日本の地震対策は、過去の惨事を教訓にしながら段階的に発展してきました。とくに明治時代以降、外国人技術者の知見や西洋建築学を取り入れつつ、日本古来の伝統木造建築が持つしなやかな耐震性を融合させてきた点が特徴的です。
近年はSNSの発達により、被災地や専門家からのリアルタイム情報が瞬時に共有されるようになり、災害時の連携もさらに強化されつつあります。
世界が注目する日本の地震対策の強みとは?
日本の地震対策は世界的にも先進的といわれています。免震・制震構造を取り入れた高層ビルや公共施設はその代表例で、震度7クラスの揺れにも耐えるよう設計されることが多いです。さらに、気象庁の緊急地震速報システムは、地震波のP波とS波の伝播速度差を利用して、本格的な揺れが到達する前に警告を発する仕組みを実現しています。

出展:気象庁ホームページ
これによって企業や公共交通機関は事前に運転を停止させたり、エレベーターを最寄り階に停止させたりするなど、二次災害のリスク低減が期待できます。また、学校教育の場でも避難訓練が頻繁に行われ、家庭内でも防災グッズを備える習慣が広がっています。以下は日本社会の持つ先進的な地震対策です。
・住環境、インフラの耐震化、不燃化耐震基準の向上や補強工事を推進し、地震による建物倒壊を防ぐ取り組みを行っています。木造密集地域や古い建物も不燃材料へ改修することで、大規模火災の発生リスクを抑えているのが特徴です。
・リアルタイムな防災情報の共有気象庁や自治体が発する緊急地震速報や津波警報を、テレビやスマートフォンなどさまざまな手段でリアルタイムに周知しています。SNSや災害情報アプリの普及により、個人間や地域コミュニティでも速やかに情報を共有できる仕組みが整っています。
・災害情報の収集、提供人工衛星やドローンなどを活用し、被災地の状況をいち早く把握して必要な支援を計画的に実施します。テレビやインターネット、ラジオなど多チャンネルでの情報発信により、被災者や国民が正確な状況を把握しやすい環境を作っています。
・さまざまな津波対策

出展:気象庁ホームページ
沿岸部の堤防や水門の整備を強化し、津波のエネルギーを減衰させるハード対策が進められています。避難タワーや高台への避難路確保といったソフト面の対策も充実しており、短時間で安全な場所に移動できる体制を整えています。
・教育機関や自治体での防災訓練の実施
学校教育や地域の防災訓練を通じて、地震発生時の正しい行動や避難方法が身につくよう指導しています。子どもから大人まで繰り返し実習することで、非常時のパニックを抑え、落ち着いた対応が期待できます。
・災害対応体制の強化
警察や消防、自衛隊などが連携し、大規模災害でも迅速に出動できるよう訓練や装備の充実を図っています。災害拠点病院の指定や医療チームの派遣体制を確立し、被災者の救護を円滑に行う仕組みが整っています。
・広域連携、支援体制の確立
地震が大規模化した際、被災地周辺の都道府県や全国の自治体が相互に支援し合う協定を締結しています。特に水や食料、医療物資などの物流ネットワークを確保し、被災直後からスムーズに補給できる体制を整えています。
・避難者、帰宅困難者への対応の充実

避難所の整備や、女性や高齢者、障害者など多様なニーズに対応したスペースの確保を進めています。交通機関が麻痺した際には、都市部での帰宅困難者受け入れ拠点を設置し、一時的な宿泊や生活必需品の支援を行っています。
・事業、業務継続性の確保
企業や行政機関はBCP(Business Continuity Plan)を策定し、災害時でも重要業務が止まらないように体制を組んでいます。データの遠隔バックアップや非常用電源の整備など、業務復旧のスピードを上げる対策が重視されています。
地震から大切な命を守るための防災アクションプラン
大規模な地震や災害に遭遇したとき、人命を最優先に守るためには普段からの備えが不可欠です。とくに、地震発生直後は道路や通信が遮断され、行政や防災組織の援助がすぐに届かない可能性があります。そんなときに備えて、最低限の非常食や飲料水、情報通信手段などを個人や家庭レベルで用意しておくことが重要です。以下では具体的な防災対策を挙げてみます。
まずは防災グッズの準備から始めよう

地震が発生すると、ライフラインが停止し、自宅や勤務先からの避難が必要になる場合があります。避難の際には手軽に持ち出せる防災リュックの準備がカギとなります。
防災リュックの中身としては、懐中電灯や電池、応急手当セット、飲料水、携帯ラジオ、タオル、現金(小銭含む)などが特に重要です。さらに、常備薬や救急用品、マスクなど、コロナ禍以降は感染症対策グッズも含めておくと安心。地域に応じて必要なもの(冬の寒冷地では保温シートなど)を選びましょう。
備蓄の常識:非常食は最低7日分!
非常食については3日分という意見も根強くありますが、近年の大規模災害では7日間程度は自力で食料を確保する必要があるとの認識が広がっています。特に水は1人1日3リットル(飲用や衛生用途を含む)を目安に準備しておくと安心です。カンパンやアルファ米、レトルト食品などは比較的長期保存が可能なため、ローリングストック法を活用して消費と補充を定期的に繰り返しましょう。
携帯回線が途絶えても困らない安否連絡手段の確保

出展:NTT東日本ホームページ
大地震発生時には携帯電話の回線が混雑し、通話やデータ通信がスムーズに利用できないケースが多々あります。公衆電話や災害用伝言ダイヤル(171)、SNSなども有効ですが、それらも状況次第ではつながりにくい状況になることが想定されます。
災害時にこそ家族や友人との連絡手段を複数持っておくことが大切です。例えば、定期的な集合場所や伝言板をあらかじめ決めるなど、オフラインでも連絡可能な体制を用意しておくとより安心できます。
ハザードマップで安全なエリアと避難経路を知っておこう
多くの自治体が公表しているハザードマップは、地震や津波、洪水など災害に対してどのエリアが危険度が高いのかを可視化したものです。防災拠点となる避難場所の場所や、危険な活断層の走向、津波の予想到達範囲などが示されています。
自宅や職場周辺のハザードマップを確認し、どこに避難すれば最も安全かを普段から把握しておくと、緊急時にも落ち着いて行動できる可能性が高まります。スマートフォンアプリや自治体のウェブサイトで詳細を確認できるところも増えているので、一度チェックしておきましょう。
停電に立ち向かう!蓄電池とポータブル電源を活用しよう
大地震のあとに最も困るのが電気の途絶です。長期化すれば連絡手段となるスマートフォンの充電はもちろん、照明や冷蔵庫など生活必需品が一切使えなくなります。
短期的&中期的な停電対策としてポータブル電源や蓄電池の導入を検討するのはとても効果的です。容量や出力の大きさに応じてスマホから小型家電までカバーできるモデルが増えており、ソーラーパネルと組み合わせれば外部電力に頼らない独立電源としても期待できます。
家具・家電の転倒を防ぎ、室内の安全を確保

室内でのケガを防ぐためには、家具や家電の転倒・落下を防止する対策が不可欠です。重心が高い棚や冷蔵庫、テレビなどは、耐震マットやL字金具、つっぱり棒などを活用してしっかり固定しておきます。
大きな揺れで倒れてきた家具に下敷きになると、大怪我や命の危険につながるリスクが高いため、手間を惜しまず行うことが大事です。特に寝室周りは安全を確保しておくと、就寝時の地震でも被害を軽減しやすいでしょう。
火の元が危険!地震後の初動と消火対策
地震直後にはガス漏れや電気系統のトラブルによる火災が多発する傾向にあります。小さな火のうちに消し止められれば被害を抑えられるので、家庭用消火器の設置は基本的な備えとして考えましょう。
消火器は使用期限や設置場所を定期的にチェックし、いざというときに使えるよう管理することが重要です。また、ガスコンロまわりの安全装置やブレーカーの位置を再確認しておき、火を使っている最中の地震でも慌てずに対応できるようにしておきたいところです。
建物被害も想定して、地震保険へ加入しておこう
日本は地震リスクが高い国なので、火災保険に加え地震保険への加入を検討する意義は大いにあります。火災保険だけでは地震・津波による建物の損害は基本的に補償されないため、自然災害による家屋の損壊リスクに備えるには地震保険が有力な選択肢です。保障範囲や保険料は居住地域によって異なるので、資料を取り寄せたり保険代理店に相談したりして自分に合ったプランを見つけると良いでしょう。
いざという時に役立つポータブル電源のおすすめ2選
災害対策の新常識とされているのが、大地震や停電時の強い味方となるポータブル電源です。近年はバッテリー技術の進歩や需要の拡大に伴い、容量や機能性がアップした製品が多数登場しています。防災リュックや非常食と同じくらい、「あってよかった」と心から思えるアイテムになるでしょう。ここではおすすめの製品を2つご紹介します。
BLUETTI AORA 100 大容量ポータブル電源 | 防災推奨 |1152Wh、1800W

日本語表示の画面とポート、ボタンにより、初心者でも直感的に操作でき、幅広い年齢層に優しい設計です。地震や台風などの災害の際、AORA 100のUPS機能は停電をわずか20msで感知し、内部バッテリーから電源供給を開始します。長期間の停電でもスマートフォンを最大18日間、電力供給できるので安心。Charger 1を使えば、車で避難する間に500Wで充電可能。ソーラーチャージも可能で、避難所でも太陽光を電力に変換してためておく事ができます。
BLUETTI Charger 1 | 560W オルタネーターDC充電器
ポータブル電源を持っている場合でも、予備の充電手段を用意しておくことが重要です。マイカーが地震に耐えた場合、Charger 1を使えば車のオルタネーターからの余剰電力を用いてポータブル電源を素早く充電し、他の必要な機械にバックアップ電源を供給することができます。たとえ広範囲な停電が続いていても、自動車を利用できる状況なら電力を確保できることが特徴。夜間や悪天候でソーラーパネル充電が使いにくい場合にも対応しやすいため、非常時における充電手段の多角化が期待できます。
まとめ
地震はいつ、どこで起きるか分からないからこそ、日頃の備えが何よりも大切です。本記事で取り上げた多発地域のランキングや被害事例、そして日本の防災対策の要点を理解すれば、いざというときの不安を大きく減らせます。ポータブル電源などの備えも加えて、今すぐ行動を始めてみてください。
あなたの一歩が、大切な人の命と暮らしを守ることにつながるでしょう。