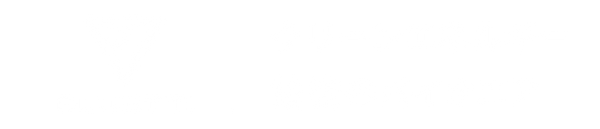地震や台風、ゲリラ豪雨など、日本に住むうえで「災害が少ない県に引っ越したい」と考える方は多いのではないでしょうか。この記事では、気象庁などのデータをもとに、地震・台風・豪雨が少ない県のランキングをテーマ別に解説。さらに、移住先として注目される「災害リスクが低い住みやすい県」や、防災対策のポイントまで詳しくご紹介します。災害の少ない地域で、安心して暮らしたい方は必見です。
【2025年】災害が少ない都道府県 総合ランキング トップ5

日本国内で頻繁に発生する三大災害といえば台風、地震、ゲリラ豪雨。それぞれの災害の発生件数を基に、災害が少ない県をランキング形式で整理しました。トップ5にランクインした都道府県は、次の通りです。
|
総合順位 |
都道府県 |
地震観測回数(2024年) |
台風の上陸回数(1951年〜2024年) |
ゲリラ豪雨の発生回数(2024年) |
|
1位 |
佐賀県 |
19回 |
0回 |
607回 |
|
2位 |
香川県 |
22回 |
0回 |
318回 |
|
3位 |
鳥取県 |
22回 |
0回 |
943回 |
|
3位 |
福岡県 |
19回 |
1回 |
1,361回 |
|
5位 |
岡山県 |
18回 |
0回 |
1,412回 |
出展:<地震>気象庁「令和6年(2024年)の地震活動について」、<台風>デジタル台風:台風上陸・通過データベース(完全版) 北本 朝展@国立情報学研究所、<ゲリラ豪雨>ウェザーニューズ
<1位> 佐賀県
地震観測回数の少なさでは全国で第2位にランクイン。九州地方に位置しているものの、これまで台風の上陸例は確認されていません。さらに、過去5年間のゲリラ豪雨発生数は全国で4番目と極めて少ない水準。
災害の発生が非常に少ないことから、総合1位の評価となりました。
<2位> 香川県
台風の接近は多いものの、上陸する例はほとんどなく被害も限定的です。過去5年間のゲリラ豪雨の発生回数は全国で最少を記録。また、2024年の地震観測回数では全国第4位と少なさが際立っています。複数の災害リスクが低水準である点が高く評価されました。
<3位> 鳥取県
2024年の地震観測回数が全国で4番目に少ない地域のひとつです。ゲリラ雷雨の発生頻度も過去5年間で全国8位と少ない傾向にあります。また、台風の接近回数が全国でも下位に位置する中国地方に属しており、総合的に災害が発生しにくい土地といえるでしょう。
<4位> 福岡県
全国の主要都市圏の中で唯一、ランキングに登場した県です。2024年の地震観測回数は佐賀県と同率で全国2位の少なさを記録。ゲリラ雷雨の発生件数は過去5年間で全国24位と中間レベルながら、台風の上陸がなく、大災害のリスクが相対的に低い地域です。
<5位> 岡山県
2024年の地震発生回数は18回と全国で最も少ない数値です。台風の上陸例がなく、揺れや風水害に見舞われる可能性が低い県といえます。一方で、ゲリラ豪雨に関しては一定の注意が必要とされますが、全体として災害リスクが非常に低く、移住先としても人気があります。
地震発生回数が少ない都道府県ランキング
続いて、地震に関連する災害データを見ていきましょう。ここでは、気象庁が公表している「震度データベース検索」の情報を基に、2024年に観測された地震が少ない県のランキングを紹介します。
|
順位 |
都道府県 |
地震観測回数(合計) |
|
1位 |
岡山県 |
18回 |
|
2位 |
福岡県、佐賀県 |
19回 |
|
2位 |
兵庫県、長崎県、奈良県 |
21回 |
|
4位 |
和歌山県、徳島県、香川県、鳥取県 |
22回 |
|
5位 |
山口県 |
25回 |
過去10年間の地震発生回数が少ない都道府県ランキング
気象庁の「震度データベース検索」によると、2015年4月5日から2025年4月4日までの10年間で、地震の観測回数が少なかった県は香川県でした。この期間における、地震の影響が少なかった県トップ10は以下の通りです。
|
順位 |
都道府県 |
地震観測回数(10年間) |
|
1位 |
香川県 |
181回 |
|
2位 |
三重県 |
186回 |
|
3位 |
滋賀県 |
194回 |
|
4位 |
奈良県 |
213回 |
|
5位 |
徳島県 |
243回 |
|
6位 |
愛知県 |
263回 |
|
7位 |
山口県 |
269回 |
|
8位 |
福井県 |
273回 |
|
9位 |
島根県 |
294回 |
|
10位 |
大阪府 |
297回 |
日本の西側で地震が少ないのは、地下でのプレート活動の影響が比較的小さいためです。日本列島の地下には「プレート」と呼ばれる4つの岩盤が存在し、これらが互いにぶつかり合うことで地震が引き起こされます。その中でも、北米プレート・太平洋プレート・フィリピン海プレートの3つが日本の東側に密集しているため、東日本では特に地震の発生が多くなる傾向があります。
南海トラフ地震において被害のリスクが低い、つまり比較的「安全」とされる都道府県は、震源域から距離があり、揺れや津波の影響を受けにくい地域です。以下は、その代表的な県です。
南海トラフ地震の被害リスクが少ないとされる都道府県

都道府県別に見ても、新潟県・栃木県・富山県は南海トラフ地震の影響を受けにくいとされ、被害のリスクが比較的低い地域です。
南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループの資料によれば、震度3以下の揺れにとどまる地域、つまり物的・人的な被害が少ないと想定される県は、福島県が唯一挙げられています。
さらに、南海トラフから距離がある北海道や青森県なども、同資料では検討対象外となっているものの、被害の可能性が低い安全なエリアと考えられます。
ただし、地震は想定外の場所でも発生する可能性があるため、どの地域でも日頃の備えは重要です。
|
都道府県 |
安全とされる理由 |
|
富山県 |
震度5以上の地震が極めて少なく、南海トラフからも離れている |
|
新潟県 |
内陸にあり、津波のリスクがなく、震源域からも距離がある |
|
栃木県 |
活断層やプレート境界の影響が比較的少なく、被害想定も小さい |
|
福島県 |
南海トラフ対策の検討資料において、震度3以下と評価された唯一の県 |
|
青森県 |
プレート境界から遠く、津波の想定被害区域にも含まれていない |
|
北海道 |
南海トラフの震源域とは離れており、直接的な影響が少ないとされる |
より詳しくは、内閣府の「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」のページを確認しましょう。
【移住するなら】自然災害が少なく住みやすい都道府県トップ5
自然災害が比較的少なく、また生活満足度や治安などを考慮し、総合的に移住先として注目される都道府県を、1位から5位までご紹介します。
1位:奈良県
奈良県では、2021年に以下のような自然災害の被害が確認されました。
-
り災世帯数:0件
-
床下浸水:10件
-
河川被害:1件
奈良県は「日本一災害に強い県」を掲げ、着実に対策を進めています。具体的には、防災情報のラジオ配信や、河川の状況をリアルタイムで監視できるシステムの導入などが挙げられます。また、有事の際に迅速な人員・物資の展開を可能にする「大規模広域防災拠点」も整備されつつあり、地域全体で災害に備える体制を強化しています。防災の面もさることながら、大阪など大都市圏へのアクセスも良好。安全と仕事や生活のバランスが取れた移住先といえます。
2位:山梨県
2021年の山梨県における自然災害による被害状況は以下の通りです。
- り災世帯数:0件
- 床上浸水:1件
- 河川被害:0件
山梨県が災害に強い理由は、行政が積極的に対策を進めてきた点にあります。2019年の東日本台風では道路網が1週間にわたり寸断され、経済と観光産業に深刻な影響が出ました。この経験を教訓に、山梨県では以下のような災害対策を導入しています。
- 水害を防ぐ治水・砂防事業の推進
- 太陽光発電設備の導入支援
- 倒木対策としての事前伐採
- 停電を防ぐための電線地中化工事
このように、実際の被害から学び抜本的な対応を進めた結果、山梨県は災害が少ない県として高い評価を得ています。山梨県内の産業はジュエリー、ワイン、絹織物、印章、和紙などの地場産業や観光、先端技術産業の工場招致など幅広い仕事の機会が見つかるでしょう。
3位:香川県
香川県では、2021年に以下のような自然災害の被害が確認されました。
- り災世帯数:0件
- 床下浸水:5件
- 河川被害:2件
このように被害件数が少ない背景には、香川県の地理的な特性があります。内海に面した穏やかな気候と、山地が少ない安定した地形により、大雨や強風による大きな被害が起こりにくいのが特徴です。
さらに、災害リスクが比較的低いため、住宅保険の保険料も抑えられる傾向があります。災害時の避難所や支援体制も整っており、高齢者や子育て世代にも安心の環境です。
生活の利便性と災害の少なさを兼ね備えた香川県は、移住を考える上で非常に魅力的な選択肢といえるでしょう。
4位:滋賀県
滋賀県では、2021年に以下のような自然災害の被害が確認されました。
- り災世帯数:7件
- 床下浸水:48件
- 河川被害:6件
一定の被害は見られるものの、滋賀県は地震や台風の被害が少ない地域として知られています。内陸に位置し、津波の心配がない点も防災面での安心材料です。
また、県全体で「災害に強いまちづくり」を進めており、防災マップの配布や避難所の整備、情報伝達体制の強化など、平時からの備えにも力を入れています。
自然環境も豊かで、生活インフラが整った滋賀県は、災害リスクを抑えながら快適に暮らせる移住先としておすすめできる地域です。
5位:群馬県
群馬県の2021年における自然災害被害は次のとおりです。
- 負傷者:4名
- 床下浸水:4件
- 河川被害:1件
群馬県では、2019年に台風19号が襲来した際、土砂災害によって4名が命を落とし、家屋の倒壊やライフラインの停止など深刻な被害が発生しました。この経験をもとに、県は「ぐんま5つのゼロ宣言」を掲げ、地域全体で災害リスクの軽減に取り組んでいます。特に防災マップの普及や、再生可能エネルギーを活用した停電対策など、災害に強いまちづくりを進めています。東京へのアクセスも良好で、都内の会社でリモートと出社を掛け合わせた仕事スタイルも可能でしょう。
災害・地震の少ない県へ移住するなら注意すべきこと

災害や地震リスクが低い地域への移住を検討する際は、その他の災害リスクや地域の防災体制についてもしっかり確認しておく必要があります。災害による被害の大小は、自治体がどれだけ防災に力を入れているかにも大きく左右されるからです。以下では、移住前に押さえておきたい3つのポイントを紹介します。
注意点1|災害リスクの高い地形や気候を避ける
移住候補地を選ぶ際は、地震だけでなく地形や気象条件による災害リスクも見落とせません。例えば、扇状地の谷口は土石流が発生しやすく、リアス海岸の湾奥では津波の被害が集中しやすい傾向があります。
また、満潮時に海面より低くなるエリアは浸水リスクが高く、年間の降水量が多い地域では河川近くの土地は避けたほうが無難です。さらに、雪に不慣れな方が豪雪地帯に移住すると、思わぬ事故につながる可能性もあるため注意が必要です。
注意点2|地域のハザードマップを事前に確認する
候補地がある程度絞れてきたら、必ず自治体が発行するハザードマップを確認しましょう。ハザードマップには、洪水・高潮・土砂災害などのリスクエリアや、災害時の避難場所が記載されています。
災害の種類ごとに分かれたマップが用意されている場合もあるため、すべてのマップを確認し、リスクの少ない場所を選ぶことが安全な移住につながります。
注意点3|地域の防災対策を把握しておく
防災意識の高い地域では、住民同士が助け合える体制が整っていることが多く、有事の際の安心感にもつながります。移住前に、その地域がどのような防災活動を行っているかを把握しておきましょう。
たとえば、以下のような取り組みが挙げられます。
- 防災ワークショップの開催
- オンラインによる防災講座
- 避難訓練や給水訓練の実施
- 情報伝達のシミュレーション訓練
これらの活動が活発な地域は、防災力の高い安心できる移住先としておすすめです。
地震が少ない地域でも備えておくべき災害対策。今日からできる防災対策7選!
地震や災害が少ない地域に住んでいても防災対策は欠かせません。なぜなら東日本大震災で経験したように「想定外」の事態が起こる可能性を否定できないからです。
気象庁は、東日本大震災と同規模の「南海トラフ巨大地震」が今後30年以内に「80%程度」の確率で発生すると発表しました。特にリスクが高いとされるのが愛知県ですが、危険なのは愛知県に限りません。静岡から宮崎にかけては震度7の強い揺れが想定されており、周辺地域でも震度6の地震や最大10m級の津波が懸念されています。
地震がいつ起こるかを正確に予測することは不可能です。大切な家族と自分の命を守るために、今から取り組める7つの防災対策をご紹介します。
1|ハザードマップで危険なエリアを確認する

出展:大田区防災ハザードマップ(事例)
災害時に危険が及ぶ地域を把握するには、市町村や国のハザードマップを活用しましょう。 地域ごとの洪水・土砂災害・高潮などのリスクが地図に記載されており、避難場所も確認できます。
引っ越しを検討中または転居したばかりの方は、自治体のホームページで防災関連情報もあわせて確認すると安心です。
2|安否確認の手段を知っておく

災害発生時は通信インフラが混乱し、電話がつながりにくくなるケースが多く見られます。確実に安否を伝える方法として以下の2つのサービスを活用しましょう。
- 災害用伝言ダイヤル(171):音声メッセージを最大30秒×20件まで登録可能(保存期間:指定なし※サービス継続中に限る)
伝言の録音方法
-
- 171をダイヤルする
- ガイダンスが流れる
- 録音の場合は「1」を押す(暗証番号を利用する場合は「3」)
- 相手の番号をダイヤルする
- メッセージを録音する
伝言の再生方法
-
- 171をダイヤルする
- ガイダンスが流れる
- 再生の場合は「2」を押す(暗証番号を利用する場合は「4」)
- 相手の番号をダイヤルする
- メッセージを再生する
- 災害用伝言板(web171):文字による伝言を最大100文字×20件登録可能(保存期間:6ヶ月)
伝言の登録方法
-
- 災害用伝言板(web171)へアクセスする
- 相手の番号を登録する
- 伝言を入力し、登録する
どちらも平常時は利用不可ですが、毎月1日・15日、1月1〜3日、1月15〜21日、8月30日〜9月5日に体験利用ができます。使い方に慣れておくことで、災害時にも落ち着いて行動できるでしょう。
3|非常食は最低1週間分を備蓄

災害後、ライフラインが復旧するまで最低でも1週間はかかると想定して準備しましょう。以下は、大人2人分の備蓄例です。
-
飲料水:2ℓ×24本、野菜ジュースや果実ジュースなど
-
主食:缶詰(肉・豆・野菜)18個、レトルト牛丼・カレー18個、レトルトパスタ6個
-
主菜:米4kg、カップ麺6個、パックご飯6個、乾麺4袋
-
副菜・果物・菓子:漬物、ドライフルーツ、保存の効く果物、飴、ビスケット、チョコなど
-
調味料:塩、味噌、砂糖、酢、醤油、マヨネーズ、ケチャップ
-
その他:カセットコンロとガスボンベ(12本)、即席味噌汁やスープなど
災害直後はコンビニやスーパーに頼れないこともあるため、備えは命綱になります。
4|家具の配置と固定を見直す

大地震では、けが人の約30〜50%が家具の転倒・落下が原因とされています。安全確保のため、以下のような対策が有効です。
-
L字金具で家具を壁にしっかり固定
-
テーブルやイスの脚に滑り止めを設置
-
キャスター付き家具のロックは常時ONに
-
ガラス部分には飛散防止フィルムを貼付
-
吊り下げ式の照明はチェーンで補強
大型家具だけでなく、食器棚やガラス扉も忘れずに対策を行いましょう。
5|子どもが使える防災グッズを備える
子どもだけでも使える防災グッズを、すぐ持ち出せるリュックにまとめておくことが大切です。主な内容は以下の通りです。
-
非常食3日分、マスク、タオル、スニーカー
-
懐中電灯、携帯ラジオ、ブランケット、レインコート
-
カイロ、マッチやろうそく、歯ブラシと歯磨き粉
-
防災ずきんやヘルメット、ばんそうこう・常備薬などの救急用品
小さなお子さんがいるご家庭は、子どもだけでも安心して行動できる準備を整えておきましょう。
6|蓄電池・ポータブル電源を備えて停電に対応

停電時でも安心して電気が使えるよう、蓄電池やポータブル電源の備えは非常に有効です。
|
種類 |
特徴 |
|
蓄電池 |
自宅据え置き型。大容量・高出力で家庭用コンセントが使用可能 |
|
ポータブル電源 |
持ち運び可能。避難所や車内でも使用可。USBポート付きでスマホ充電にも便利 |
津波や浸水リスクのない住宅に住んでいるなら蓄電池が良いですが、移動の可能性がある場合はポータブル電源が適しています。
7|支援を受けられる施設の場所を事前に確認する
災害発生後、自宅に戻れない場合や帰宅困難となった際に頼れるのが「災害時帰宅支援ステーション」です。発災から72時間後を目安に、以下の施設で利用が可能です。
-
コンビニエンスストア
-
ファミリーレストラン
-
ガソリンスタンド など
支援内容には、水・トイレの提供、休憩所の開放、道路情報の案内などがあります。事前に市町村のホームページで近隣の支援施設を確認しておくことが重要です。
災害時の停電でも家電が使える!非常用電源のおすすめ
地震や台風・ゲリラ豪雨などで停電が発生した際、生活を維持する鍵となるのが非常用の電源です。中でもおすすめなのが、ポータブル電源とソーラーパネルのセット。組み合わせて使えば、電源のない環境でも長時間にわたり家電を使用することが可能です。
ポータブル電源があれば、こんなときに役立ちます:
-
スマートフォンを充電し、連絡や情報収集が継続できる
-
エアコンや電気毛布で暑さ・寒さをしのげる
-
電子レンジでレトルト食品や温かい飲み物を調理できる
さらに、ソーラーパネルがあれば、ポータブル電源の再充電が可能。停電が長引いても電力を確保でき、数日間にわたる避難生活でも安心です。
中でもおすすめなのが、BLUETTI(ブルーティ)製のポータブル電源です。
-
日本専用設計のAORAポータブル電源をラインナップ
-
防災安全協会に認められた「防災製品等推奨品」
-
業界高水準の5年保証付き
-
グッドデザイン賞を受賞(2021年)
停電時でも家族の安全と快適を守るために、信頼できるポータブル電源の備えを今のうちに検討しておくことをおすすめします。
BLUETTI AORA 100 大容量ポータブル電源 | 災害時にも日常と変わらぬ電力を

1時間の充電で1日分の電力が確保できる大容量モデル。地震の際には、非常用電源AORA 100のUPS機能は停電をわずか20msで感知し、内部バッテリーから電源供給を開始します。最新リフト機能が電圧を調整することで、2700W以下の電熱製品(電気ポットやドライヤーなど)も使用可能に。1,152Whの大容量バッテリー搭載なら、以下のシーンで活躍します。
-
長期間の停電でもスマートフォンを最大58回充電
-
停電時の光となるライトも88時間も使用できる
-
寒さをしのぐ電気毛布を14時間も使える
長引く停電にも対応できるよう、太陽光ソーラーパネルでの充電も可能です。Charger 1と組み合わせて使えば、車で避難する間にも余剰電力を用いて充電ができ、避難先での電力を確保できます。
AORA80小型ポータブル電源:災害時に強いコンパクト設計

防災電源AORA80はよりコンパクトで軽量なモデル。最大2000Wの高出力機器にも対応できる「電力リフトモード」を搭載し、冷蔵庫や電気ケトルなど、災害時に最も必要な機器に安定した電力供給が可能です。コンパクトで持ち運びやすいのにパワフルなAORA80なら
-
最大45回のスマートフォン充電が可能
-
暑さに耐える扇風機を12.5時間使用
-
寒さに負けない電気毛布は9.7時間使用
など、地震の際にも大切な人との連絡手段を確保し、体調を維持することができます。
地震・災害対策に関するよくある質問(FAQ)
Q: 「地震が少ない県」は何を基準に決められていますか?
A: 地震の少なさは、気象庁の「震度データベース」や各年の観測回数、震度5以上の発生頻度、さらには過去10年間の累計地震回数などを基に評価しています。震度の大きさだけでなく、継続的な揺れの有無や地質構造なども判断材料に含まれています。
Q: お金をかけずにできる地震対策はありますか?
A: 高価な備蓄品や設備がなくてもできる対策は多くあります。たとえば、寝室に倒れやすい家具を置かない、ガラスの飛散を防ぐために窓に養生テープを貼る、懐中電灯や笛を枕元に置くなど、日常生活の延長でできる工夫があります。また、家族と避難場所や連絡方法を事前に話し合っておくことも、費用のかからない重要な備えです。
まとめ
災害が少ない県に住んでいてもいなくても、災害への備えが日々の安心につながります。あなたの住むエリアの地震・台風・豪雨のリスクを知り、防災対策を整えておくことが、万が一の時にあなたの命を守ります。大切な人との日常を守るために、今こそ備えを前向きに考えてみませんか?