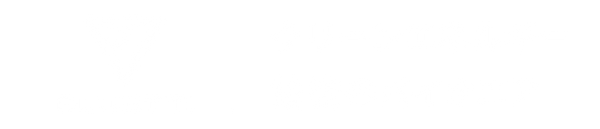ポータブル電源を選ぶ際に悩むのは「出力」と「容量」ではないでしょうか。
容量に関して言えば、小さいものは200Wh~300Whから大きなものは5,000Whまで様々な容量のポータブル電源があります。
容量の小さなポータブル電源は、何にどのぐらい使えるのかを想像しやすいですが、容量の大きなポータブル電源ほどどう使えばいいのかが良く分からない傾向にあります。
そこで今回は、5,000Whを誇るBLUETTIの大容量ポータブル電源「EP500」を事例に、「何に」「どれぐらい」使えるのかを検証してみようと思います。
ポータブル電源ってなに?どうやって使うの?
そもそもポータブル電源とはいったいどのような製品を指すのでしょうか。そしてどのような使い方をするのか、使用する際の注意点はあるのかなど、まずはポータブル電源の基礎知識をおさらいしておきましょう。
ポータブル電源とは
ポータブル電源とは、読んで字のごとく「ポータブル(持ち運び可能)」な「電源(蓄電池)」です。つまり、電気を貯めておいて、使いたい場所へ移動し、好きな時に電気を取り出して電気製品などに使うことができる製品のことです。
コンパクトで手で持ち運ぶタイプが真っ先に思いあたりますが、キャスターで移動するタイプもポータブル電源です。
また昨今では、ポータブル電源本体と、容量を拡張する「拡張バッテリー」が切り離せるタイプが増えており、切り離して本体のみを移動する、あるいは本体・拡張バッテリー両方を移動するなど、電源の移動にもバリエーションが増えています。
ポータブル電源を使う際の原則
ポータブル電源には、電力を連続して供給し続けられる力「定格出力」があります。また瞬間的に大きな電力を供給できる「瞬間最大出力」もあります。
一方で、電気製品にはその製品が正常に動作するために必要な電力として「消費電力」が定まっています。
この「定格出力」と「消費電力」の関係は、必ず『定格出力>消費電力』でなくてはなりません。定格電力が消費電力より小さい場合には、その電気製品は動作しません。例えば、定格出力800Wのポータブル電源では、消費電力1000Wの電子レンジは使えません。
従って、ポータブル電源の購入を検討する際には、使用する予定の電気製品の消費電力を定格出力が上回っているかを確認する必要があります。
瞬間最大出力は、電気製品が瞬間的に大電力を必要とした際に対応できる能力です。多くの場合、瞬間最大出力は定格出力の2倍程度です。
5000Whの大容量ポータブル電源をどう使う?
それではここからは、BLUETTIの大容量ポータブル電源「EP500」を事例に、5000Whの電力をどう使うのか、何に使えるのかを検証してゆきたいと思います。
家庭で使う

まずは身近なところで「家庭内」で使うことを考えてみましょう。
家庭内でもすべての場所にコンセントがあるわけではないので、移動できる電源としてポータブル電源が1台あると重宝します。EP500はキャスター付きなので電源が欲しい場所に簡単に移動させることができます。
長い延長コードを使わなくても付属の電源コードだけで家電を動かすことができ、家事の負担を低減することができます。
1つ提案なのですが、家庭での活用方法として「クリスマス・イルミネーション」はいかがでしょう。庭や垣根、玄関などにクリスマスのデコレーションを施して、色とりどりのイルミネーションを点灯させればクリスマス気分も一気に盛り上がります。
秘話や玄関に電源コンセントがなくてもポータブル電源があれば好きな場所にイルミネーションを点灯できます。また、昼間のうちにソーラー発電で貯めた電気で点灯させれば電気料金を発生させずにイルミネーションを楽しめます。きっと、クリスマスをもっと楽しめるに違いありません。
電源のない場所で使う

例えば、個人宅では庭でのガーデニングや、駐車場やガレージでの洗車・メンテナンスなどに、近くにコンセントがない場合でもキャスター付きのEP500なら必要な場所へ電源を移動できます。
また、業務においても、公園やガーデン施設などのメンテナンスにも電動園芸機器が活躍しますし、マンション管理でもコンセントのないエリアでの管理業務に役立ちます。
ここでの提案は「お庭バーベキュー」です。薪や炭を起こしてするバーベキューは火おこしや後片付けが大変ですが、ホットプレートを庭に持ち出して簡単な鉄板焼きバーベキューはいかがでしょう。
もちろん電源はポータブル電源から。EP500なら消費電力の大きなホットプレートでも余裕で稼働できるので、ちょっとしたガーデンパーティを手軽に楽しめます。
屋外イベント、アウトドアで使う

お祭りや縁日、フェス等のイベントなどでもポータブル電源が活躍します。
従来は発電機を使っていた場面でも、昨今は燃料を使用する発電機に代わって安全性の高い大容量ポータブル電源で代用する場面が増えています。
照明やイルミネーションはもちろん、最近では「かき氷器」や「ポップコーン」「わた菓子」なども電気製品なので、お祭りや縁日、イベントなどでも大容量の電力確保が重要になっています。
もちろん、キャンプやバーベキュー、様々なアクティビティなどのアウトドアレジャーにも電力確保は必須です。
何をどう使うかにもよりますが、600Wh~700Whあれば1泊キャンプや車中泊には充分と言われますので、5000Whもあれば1週間の連続キャンプも楽々こなします。
仕事に使う

画像出典:unsplash.com
5000Whもの容量があれば仕事や業務で使用するにも十分です。
例えば夜間作業時のサーチライトや投光器、サーキュレーターや工業扇、スポットクーラー、冷蔵庫などを使用することが可能です。
また、草刈り機や計測器など充電式が多い機器についても、予備バッテリーを充電しておけば、バッテリ交換がその場でできるため作業効率がアップします。
ちなみにEP500は容量5000Whに耳目が集まりやすいですが、定格2000W/最大4800Wの出力を備えているので、比較的消費電力が大きい業務用機器にも十分対応可能です。
電動工具を使う

筆者は商用バンを車中泊仕様に改造したクルマを所有しており、自分の好みで改造やカスタムをする際に、駐車場に電源がなく庭のコンセントから延長ケーブルを使用しています。手持ちのポータブル電源では出力が足りずに使えないのです。
電動工具は家庭内での使用を前提としていないので、家庭用コンセントの1500Wを超える機器も少なくないため、小~中クラスの電源では動作させられない場合が多いのですが、定格2000WのEP500であれば、電動工具も難なく動作します。
「丸のこ」や「ドリル」「グラインダー」「ベルトサンダー」「集塵機」などはどれも1000~1500Wの消費電力で、容量の小さな電源では「あっ」という間に容量を使い切ってしまいます(その前に出力不足で動作しませんが)。
その辺りは5000Whもの容量を持つ大容量ポータブル電源の出番と言えます。
また、最近の工具の多くは充電式ですが、パワーを要する工具は電源に繋ぐタイプもいくつかありますし予備バッテリーを充電しておけばすぐに交換できて充電待ちがなくなります。
節電に使う

ポータブル電源とソーラーパネルの組み合わせは家庭内の「節電」に貢献します。
例えば「電気を食う」家電として暖房器具があります。小型のセラミックヒーターでも700~800W、大型の製品では1200~1400Wの消費電力ですが、5000Whの容量を持つEP500から給電した場合には、700Wで最大7.1時間、大型でも4.1時間も連続運転が可能です。
この電力をソーラーパネルの太陽光発電で蓄電した場合には、グリッド(壁コンセント)からの電気使用量が減ることとなり、その分「節電」することが可能です。
電気は、ガス、水道などのエネルギーやライフラインの中で唯一「自給」可能なエネルギーです。ソーラーパネルを日向に接地するだけで簡単に発電することができ、ケーブルを繋ぐだけでポータブル電源に蓄電することが可能です。
毎日1000Wのセラミックヒーターを5時間使用した場合の電気料金は4,050円/月(1kWh=27円で計算)になります。ソーラーパネルによる自給で得られた電気で賄った場合には、月間4,050円、1シーズン(11月~3月の5ヵ月)で20,250円もの節約になります。
防災備蓄~災害時の電源確保

引用:「東日本大震災におけるライフライン復旧概況(時系列編)」岐阜大学工学部社会基盤工学科
https://committees.jsce.or.jp/2011quake/system/files/110603-ver3.pdf
こちらのグラフは、東日本大震災時のライフラインの復旧状況を調査した際の停電戸数の推移ですが、震災発生の翌日にはほとんどの停電が解消されていることがわかります。

引用:「東日本大震災におけるライフライン復旧概況(時系列編)」岐阜大学工学部社会基盤工学科
https://committees.jsce.or.jp/2011quake/system/files/110603-ver3.pdf
一方こちらは同じ調査でのガスの供給停止の推移です。災害発生時に45万戸だったガス停止戸数は20日間経過してやっとおよそ半数に減少しています。
このようにライフラインの中でも電気は復旧が早いことが特徴です。それは送電設備の多くが地表にあるためで、ガス管を地中に埋設しているガスの復旧状況との決定的な差となっています。
一方、個人や家庭の場合でも、ガスに比べて電気ははるかに「自給」しやすいエネルギーです。ソーラーパネルと太陽光さえあれば手軽に電気を生み出すことが可能です。自ら生み出した電気を蓄電池に貯めておき、必要な時に使用することも可能です。
ガスの場合は、個人が対策できるのはカセットコンロとガスボンベ(CB缶)、キャンプ用バーナーとガスボンベ(OD缶)といった程度です。しかもスマホ充電や照明、調理、暑さ寒さへの対応など様々に対応可能な電気に比べて、適用範囲が狭いのが特徴です。
こちらは想定した災害停電時の生存のための4人家族の電気製品の使用シミュレーションです。
| 項目 | 容量 | 数量 | 総容量 | 消費電力 | 使用時間 | 総消費電力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマホ充電 | 5000mAh | 4 | 20000mAh | 18.5Whx4(※) | 74Wh | |
| LEDランタン充電 | 5000mAh | 3 | 15000mAh | 18.5Whx3(※) | 55.5Wh | |
| ポータブル冷蔵庫 | 45~55W | 1 | 50Wh | 24時間 | 1200Wh | |
| 扇風機(電気毛布) | 50W | 2 | 100Wh | 7時間 | 700Wh | |
| 炊飯器 | 250W | 2 | 500Wh | 1時間以内 | 500Wh |
・情報収集や連絡のために欠かせないスマートフォンは4台を1日1回フル充電します。
・夜間の灯りとして、5000mAhのLEDランタンを3台用意しておきます。
・食品などを保存するためのポータブル冷蔵庫(30L)で50Wh×24時間稼働します。
・夏場は避暑に扇風機、冬場は防寒に電気毛布を2台(2枚)使います。
・小型の2合炊き程度の炊飯器で米を炊きます。
以上のように、かなり絞り込んだ電気使用例でも1日に2,529.5Whの電気を消費します。
通常大容量と言われる2000Wh容量のポータブル電源でも1日も持ちません。仮に最も電力を消費する冷蔵庫を外しても1,329.5Wh必要です。
それでももし、350Wソーラーパネルを備えてあり晴天に恵まれれば最大出力の70~80%の発電量を得られるはずなので、日照時間を5時間と仮定すると1日に1400Wを発電できると想定できます。
冷蔵庫ナシであれば、350Wソーラーパネルの発電量で1日分の電力消費を賄うことができます。冷蔵庫ありの場合には、1日に1,029.5Whずつ充電量が減少してゆきます。
EP500は5,000Whの容量を持っているので、冷蔵庫ありで1129.5W/日ずつ容量が減少したとしても4~5日は電力を確保し続けられ、冒頭の資料のように復旧の早い電気の供給が再開するまで電力を持たせることが可能かもしれません。
災害への備えを検討する際には、何にどれぐらいの電力を使うのかを各家庭でシミュレーションして、蓄電容量と発電量を決めるとよいでしょう。
BLUETTI EP500 家庭用バックアップ可搬型電源 購入がこちら
5000Whの大容量ポータブル電源 まとめ
今回の記事では大容量5,000Whの使い道についてご紹介いたしました。
一般家庭でも、事業所でもあれば必ず役に立つ電源だと感じました。例えばマンションの備品として購入しておき、災害時には住人の電力補助に使ってもいいのかな…などと色々なことが頭に浮かびます。
皆さんにもアイデアを駆使してEP500を使いこなして欲しいと思います。